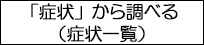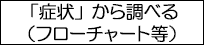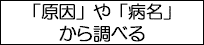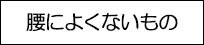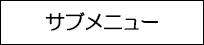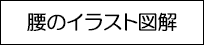坐骨神経痛で腰が痛むケース
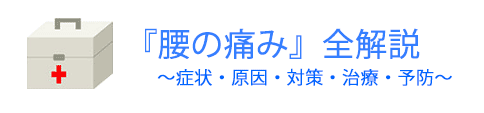
『坐骨神経痛』の詳細 - 症状・原因・治療法
腰痛を引き起こす可能性のある病気や障害の一つに「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」があります。ここでは、その特徴や腰痛との関連について解説します。
<目 次>
スポンサーリンク
1.坐骨神経痛が疑われる症状
腰の痛みのほかに、以下の様な症状・特徴が見られる場合、坐骨神経痛が発症している可能性があります。
|
最も特徴的な症状は、下半身の広い範囲に起こる「激しく鋭い痛み」と「しびれ」です。
痛みは腰を動かすと強まり、安静にしていても続くことが多いです。ひどいケースでは、足やお尻の痛みのせいで長く立っていたり座っていることができず、夜も痛みで眠れないこともあります。
◆痛み方
皮膚の表面近くが激しく痛みます。また、多くの神経痛は瞬間的な痛みですが、坐骨神経痛は痛みが連続することが多いです。
◆発生する箇所
腰やお尻、太ももの裏側、ふくらはぎなどに起こり、更に足首からカカト、つま先にまで響くこともあります。どこか一部だけのこともあれば足全体に広がるようなケースもあり、どの位置の神経が障害を受けているかによって変わります。また、通常左右どちらか一方の足に起こり、足の外側にそって痛むことが多いです。
◆こんな症状が現れることも
- 足にダルさや冷えを感じる
- 足の感覚が鈍くなる、腱反射の異常がみられる
- 腰や足の激しい痛みで歩けない(歩行障害)
- 「寒い時」、「夕方」、「天気が崩れそうな時」などに痛みやしびれがひどくなる
→気圧の変化などによって患部周辺の血管が収縮することが関係しているといわれます
2.坐骨神経痛とは? - 特徴や原因
脳から腰に向かって伸びる一本の太い中枢神経「脊髄」は、腰のあたりで馬尾神経という細い神経の束になり、更に腰椎や仙骨の間を通って足先に向かい枝分かれしていきます。この一部がお尻のあたりで合流して坐骨神経という一本の神経になります。
坐骨神経は最も太い部分は直径1cmほど、全長は1m以上に達する太い神経です。お尻~太ももの後ろ側を通って下降し、途中で脛骨神経と腓骨神経に分かれて足先まで伸びていきます。
坐骨神経がなんらかの原因で圧迫を受けたり炎症を起こしたりすると、神経の支配する部位で強い痛みやしびれが生じます。これが坐骨神経痛です。
1mもの長さのある坐骨神経は、太ももから足先まで広い範囲の知覚をつかさどっているため、腰から足の裏にいたる広い部分に痛みをもたらします。神経痛のなかで最も起こりやすいものです。
◆坐骨神経を刺激する要因
主な要因は、腰部の骨である腰椎や仙椎に起こる障害です。
下記のような病気になると、坐骨神経が刺激・圧迫されて神経痛の症状が発生することがあります。
- 腰椎椎間板ヘルニア
坐骨神経痛の原因として最も多いものです。椎間板が押しつぶされて飛び出した髄核(ヘルニア)が神経を圧迫します。 - 腰部脊柱管狭窄症
神経の通り道である「脊柱管」が、加齢や病気によって狭くなり神経が圧迫されます。 - 腰椎分離症・すべり症
腰椎は椎骨と椎間板が積み重なってできており椎間関節でつながっています。椎間関節が疲労骨折すると椎骨がずれ動いて神経を圧迫します。 - 変形性腰椎症
腰椎を構成する骨(椎骨)が、加齢や負担の蓄積でトゲ状に変形して神経を刺激します。 - 脊髄腫瘍
脊髄やその周辺にできた腫瘍が大きくなって神経を圧迫します。
そのほか、帯状疱疹、糖尿病、うつ病、リウマチ、アルコール依存症などが原因となることもあります。
◆痛みを悪化させる要因
前述した腰椎の障害に別の要因が加わることで、坐骨神経痛による痛みが増したり長引いたりすることがあります。
- 筋肉や靭帯の疲労、冷え
腰椎に障害が起きている場合、大抵は腰まわりの筋肉や靭帯に疲労が見られます。これは筋肉が弱った結果として腰椎障害が起きていたり、逆に腰椎障害で不安定になった腰を支えるために腰まわりの筋肉や靭帯に余計な負担がかかるためです。
腰を使いすぎたり冷やしたりすると、筋肉や靭帯が緊張して固くなり、コリができたり血行が悪くなることで坐骨神経痛の症状を悪化させます。 - 精神的な不安やストレス
心労が重なると、痛みをブロックする機能が低下したり、体の機能をコントロールする自律神経のバランスが崩れて、痛みを強く感じるようになります(参考:ストレスによる痛み) - 長期間の圧迫
神経が長期にわたって圧迫され続けると、神経の炎症が強まったり、自然回復しないほど損傷することがあります。こうなると、神経の圧迫を取り除いた後もしばらく痛みやしびれが続いたり、完全には治らなくなることがあります。
3.診断・治療・予防
◆診断
下半身の痛みやしびれは坐骨神経痛に特有の症状であるため、坐骨神経に障害が起きていることは容易に判断がつきます。
そのほか、体を動かした時の反応から神経に異常があるかどうかを調べる神経学的検査も行われます。
神経のどの部位に異常があるかは、痛みやしびれが起こる箇所を詳しく聴きとることで大体分かります。これは腰から枝分かれしている神経がそれぞれ別の部位の感覚を支配しているためです(図参照)。
障害が起きている箇所にあたりをつけたら、MRI、CTスキャンなどの画像検査を行い、神経を圧迫している原因を探ります。神経を圧迫しているのは椎間板や靭帯などの軟性組織であることが殆どであるため、骨しか映せないX線検査(レントゲン)では詳しい状況が分からないことが多いです。
【関連項目】
原因不明なケースも
画像検査の結果、腰まわりの骨、椎間板、神経などに異常が見られず、明らかな原因を特定できないこともあります。こうした腰痛を「非特異的腰痛」といいます。
非特異的腰痛のうち、神経のどこかに圧迫や障害がある神経性の痛みと思われる場合は「坐骨神経痛」と診断され、筋肉の疲労やケガ、関節や靭帯の損傷など、神経以外の要因による痛みと思われれば「腰痛症」と診断されます。
非特異的腰痛は腰痛全体の85%を占めます。つまり腰痛の多くは「~が原因だ!」とはっきり断定できないことが多いのです。
◆治療
前述したような坐骨神経を刺激する病気や障害を特定し、その治療を行います。
神経のどこかに圧迫や障害があることは分かっても、何が神経を害しているのか分からない場合は、以下のような一般的な腰痛治療を行います。
- 運動療法 : 筋力トレーニング、ウォーキング、腰痛体操などの様々な運動を行うことで、腰を支える力を強くしたり、血行促進やストレス解消を図る
- 薬物療法 : 炎症を抑えて痛みを和らげる薬(消炎鎮痛剤)を服用したり、神経に麻酔をかけて痛みを感じなくする神経ブロックの注射を行う
- 温熱療法 : ホットパックや超音波を利用して腰を温め血行を促進する。筋肉のコリをほぐしたり、痛みや疲労の回復を早める効果がある
- 装具療法 : 腰用のコルセットなどの装具を装着し、腰の負担を軽くしたり外部からの衝撃を和らげる
こうした保存的療法(手術を行わない治療)を、症状に応じて組合せて行います。
日常生活においては腰の負担の大きい姿勢や作業を極力ひかえるようにします。
【参考】
また、精神的ストレスなどの心の病が絡んでいるケースもあります。
原因不明の非特異的腰痛の3分の2には、不安やストレス、鬱(うつ)などの心理的要因が関与していることが研究の結果から明らかになっています。
こうした場合、神経を障害している病気を治療しただけでは症状が完全に消えなかったり、すぐに再発してしまうケースも多く、精神的な問題も解決していく必要があります。詳しくは心因性腰痛で解説しています。
再発について
坐骨神経痛は、症状がおさまって完全に治ったと思っていても、腰を伸ばしたりひねったりなどの些細な動作から再び発症することが少なくありません。
普段から腰を使いすぎたり腰によくない姿勢を続けないよう気を配り、腰を強くするために適度な運動を定期的に行って再発を予防しましょう。
【参考】
4.坐骨神経痛データ
【受診科】
- 腰椎障害の治療なら「整形外科」、神経の状態を調べるなら「神経内科」
【坐骨神経痛の症状がみられる病気】
- 腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症、腰椎分離症・すべり症、脊髄腫瘍、
帯状疱疹、糖尿病、うつ病、リウマチ、アルコール依存症