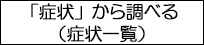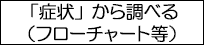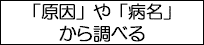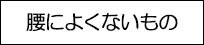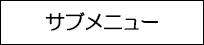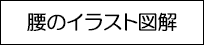子宮がんで腰が痛むケース
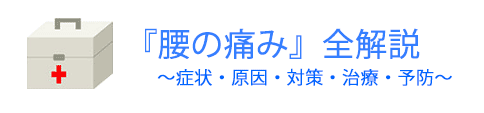
『子宮がん(子宮頸がん・子宮体がん)』の詳細 - 症状・原因・治療法
腰痛を引き起こす可能性のある病気や障害の一つに子宮がんがあります。
ここでは、その特徴や腰痛との関連について解説します。
1.子宮がんが疑われる症状
腰の痛みのほかに、以下の様な症状・特徴が見られる場合、子宮がんが発症している可能性があります。
|
がんの初期はほとんど自覚症状がありません。
病気が進行すると、がんから出血することによって「月経時以外の性器からの出血」、「血の混じったおりものやピンクのおりものがでる」、「セックス中の出血」、「貧血」などの症状が現れてきます。
また、おりものの量が増えるのも特徴的な症状です。
ほかには、がんの病巣で細菌感染が起きた場合には腹痛や発熱が見られます。
がんが周辺臓器へ転移すると、おしっこの回数が増える(頻尿)、尿が出にくい(排尿困難)、下腹部の痛み、腰痛、足の痛み、むくみなどが起こることもあります。
2.子宮がんとは? - 特徴や原因
子宮にできる悪性腫瘍(がん)を総称して子宮がんといいます。
がんの発生箇所によって名称が変わります。膣に近い子宮の出入口付近を「子宮頸部」といい、ここにできたがんを子宮頸がんと呼びます。
子宮の奥の妊娠時に胎児が発育する空間を「子宮体部」といい、ここにできたがんを子宮体がんと呼びます。
患者数はほぼ半々で、子宮頸がんの方が若干多くなります。
◆子宮頸がんについて
子宮頸がんが多く発症する年代は、20~40代および70代です。
近年は高齢者の発症数は減少傾向にありますが、逆に20~30代の若い世代で増加していて死亡率も増えていることから、若年者の子宮頸がんの増加が問題になっています。
がんは最初のうちは組織の表面の浅い部分にとどまっていますが、徐々に奥深くまで広がっていきます。子宮を支える靭帯や膣に広がり、さらに膀胱や直腸などの周辺臓器に転移していきます。また、骨盤内のリンパ節や血管を介して遠くの臓器に転移していくこともあります。
がんが発生する原因
完全に解明されてはいませんが、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が主な原因の一つであることが分かっています。
子宮頸がん患者の90%以上からこのウイルスが発見されており、性行為によって感染します。感染したから必ずがんになるというわけではなく、多くの場合、体の免疫力によって2年ほどでウイルスは消滅します。ですが強力な種類のウイルスに感染したり、免疫力が弱まっていたりすると感染が持続して子宮頸がんを発症します。
発症までには何年もの長い年月がかかり、発症率は20%程度とされます。
ウイルス以外では、性交開始年齢が早い人、性交相手が多い人、多産の人などに発症しやすい傾向があります。
◆子宮体がんについて
50~60代の閉経後の女性に多く見られます。以前は日本人にはあまり見られませんでしたが、年々増加して今では子宮がん全体の約4割を占めるほどになっています。
子宮体がんは発生場所が子宮の奥なので発見しにくいがんの一つといわれます。
はじめに子宮内膜から発生し、初期は内膜の中にとどまっていますが、徐々に奥の子宮筋層内に広がっていき、最終的には子宮の外側まで達してお腹全体(腹腔内)に広がっていきます。
がんが発生する原因
乳がんと同じく女性ホルモンのエストロゲンが長期間分泌されると発症しやすいといわれます。
エストロゲンの分泌量が多すぎると月経不順が起こりやすいため、30~40代で月経不順が長く続いている女性は注意が必要です。
また、閉経後の高齢女性に多くみられるなど、ホルモンとは関係なく発症するケースも多いです。高齢になってから発症するものは、がんの悪性度がやや高い傾向があります。
他の危険因子としては、未婚、不妊、初婚年齢や初妊娠年齢の高さなどがあります。
子宮頸がんが多産婦に多いのに対し、子宮体がんは未産婦に多く見られます。
3.診断・治療・予防
◆診断
子宮がん検診では、細胞診、コルポスコープ診(膣拡大鏡診)、組織診という3つの方法を組み合わせて診断します。
- 細胞診
綿棒やヘラで子宮の入口の細胞を取り、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる方法。全く苦痛はなく短時間で検査が可能。 - コルポスコープ診
細胞診で異常が見つかった場合に、コルポスコープという機器で細胞片を拡大して観察し、細かい変化までとらえて病変部分を摘出する。 - 組織診
コルポスコープ診で摘出した組織片を更に精密に検査する。
これらの診断によってがんの存在が確認できたら、治療法を決めるために、直腸診、膀胱診、腎盂尿道造影法などの検査を行います。
◆治療
一般的ながんの治療法と同じで、がん組織を切除する「手術療法」、放射線を照射してがん組織を死滅させる「放射線療法」、抗がん剤を投与してがん細胞の増殖を抑える「化学療法」が中心です。
がんの進行度合いや患者の状態に応じて、これらの治療法を組合せて行います。手術後に妊娠・出産を希望するかどうかも考慮されます。
がんに至る前の段階
腫瘍が完全にがん化する前であれば、通院して様子を見ながら自然治癒を待ちます。
初期がんの場合
がんが組織の奥深くまで広がっていない軽度の状態であれば、がんに侵された病変部分のみを切除する手術を行います(円錐切除術など)。そのほかレーザー光線でがんを死滅させるレーザー蒸散術、高周波でがんを殺す高周波療法、がんを凍らせて死滅させる冷凍療法などもあります。
子宮体がんの場合は、がんの増殖を抑えるホルモン(プロゲステロン)を投与するホルモン療法が行われることもあります。
こうした治療法であれば、大抵の場合、子宮を温存することができます。妊娠を希望しない場合には、がんの再発を防ぐために子宮を摘出することもあります。
進行がんの場合
がんが進行している場合は、子宮だけをとる「単純子宮全摘術」や、子宮の周辺組織も摘出する「広汎子宮全摘出術」を病状に応じて行います。将来子どもが欲しい人に限っては病変部分だけの切除に留め、子宮を温存することもあります。
がんが広範囲に広がっていたり転移が起きていると、全ての病巣を残さず切除するのは難しくなります。また体力のない高齢者であったり、がん以外の病気も合併していて手術ができないこともあります。こうしたケースでは手術のほかに放射線療法や化学療法が行われます。化学療法はがんの再発予防にも高い効果があります。
これらの治療法を併せて行うことで、従来よりもすぐれた治療成績を残せるようになりました。
手術後
進行したがんほど再発も多くなり、進行程度によって20~70%の再発があります。
治療後も再発の有無や後遺症チェックのため、引き続き通院して定期的に検査を受けることが非常に大切です。
手術後に現れやすい後遺症には、尿漏れなどの排尿障害や足のむくみがあります。卵巣を摘出した場合は、めまい、肩こり、息切れ、発汗などの更年期障害に似た症状も現れます。
◆予防
月経外の性器出血やおりものの変化は、子宮がんに特徴的な症状ですが、これらは疲れやストレスでホルモンバランスが乱れたり、他の性器の病気になった時にも比較的よく見られるものです。そのため深刻に考えずに放置されてしまいがちで、がんの発見が遅れることがあります。
また、子宮がんは初期の自覚症状が現れないことが多いため、月経に異常が生じたら念のため産婦人科で検診を受けることが大切です。
子宮がんは早期に発見すれば手術で治る病気です。
がんの中ではかかりやすい部類に入りますが、近年の子宮がん検診の広まりによって早期発見が可能になり治りやすくなりました。
20歳からは2年に1回、費用の全額もしくは大部分が公費でまかなわれる「子宮がん検診(子宮頸がん検診)」が受けられますので、積極的に利用しましょう。
なお、子宮体がんは高齢者に多いがんであるため子宮がん検診の対象にはなっておらず、全額自費による検査になります。
4.子宮がんデータ
【受診科】
- 婦人科
【子宮がんの原因となる病気】
- 子宮筋腫(ごくまれに)
【関連項目】