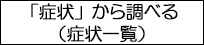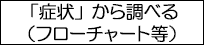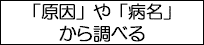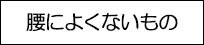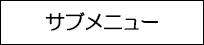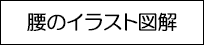尿路結石で腰が痛むケース
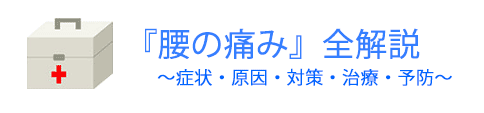
『尿路結石』の詳細 - 症状・原因・治療法
腰痛を引き起こす可能性のある病気や障害の一つに「尿路結石(にょうろけっせき)」があります。
ここでは、その特徴や腰痛との関連について解説します。
1.尿路結石が疑われる症状
以下に示すような"腰痛の特徴"や"腰痛以外の症状"が見られる時は、「尿路結石」が発症している可能性があります。
|
尿路に結石ができると、左右どちらかのわき腹から背中にかけての痛みが発生します。
冷や汗や吐き気をともなう"突然の耐え難い激痛"であることが多く、痛みは断続的に続き、腰にまで響くこともあります。
鈍い痛みだけのこともありますが、大抵は激しい痛みのために病院へ行くか救急車で運ばれることになります。
また、結石が尿路を傷つけたり膀胱を刺激すると以下のような排尿障害が起こります。
- 血の混じった真っ赤な尿(血尿)が出る
- 頻繁に尿意を感じてトイレの回数が増える(頻尿)
- 尿が細くて出にくかったり、途中で途切れてしまったりする
- 尿をする時に痛みを感じる(排尿痛)
- 排尿後も尿が残っている感じがする(残尿感)
そのほか、膀胱に結石があると排尿時以外でも下腹部に痛みを感じたり、結石による傷で細菌感染して熱がでることもあります。結石が尿といっしょに体の外に排出されることもあります。
◆石ができる場所による症状の違い
尿路結石は、結石ができる箇所によって、腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石に分けられます。
それぞれ症状の程度や現れやすさに若干の違いはありますが、主な症状は共通していますので、細かい違いについては省略します。
2.尿路結石とは? - 特徴や原因
腎臓の主な働きは、血液を濾過して老廃物を取り除き「尿」にすることです。
腎臓で作られた尿は、腎臓~尿管~膀胱(ぼうこう)~尿道の順に、上から下へ流れて体外へ排出されます。この一連の通路のことを「尿路」といいます。
この尿路にできた石(結石)を総称して尿路結石と呼びます。
結石ができた場所によってそれぞれ腎結石、尿管結石、膀胱結石、尿道結石と呼ばれ区別されることもあります。
男性の発症率が高く、女性の2~3倍です。年齢別では、30~50歳代に多く見られます。
結石はそれぞれの場所でできることもあれば、腎臓など上流でできたものが尿といっしょに流れて移動することもあります。結石が腎臓にあるうちは痛みがなくても、尿管以下まで流れて詰まると、尿管が傷つき激痛が起きます。
結石は1個のことが多く、2個以上あることは比較的珍しいケースです。
◆結石ができる原因
結石は尿に含まれるシュウ酸やリン酸などの成分にカルシウムが結合して結晶化したものです。
何らかの原因によって尿路が狭くなったり、尿がうまく流れずに停滞したり、カルシウムの濃度が高まったりすると結石ができやすくなります。
結石の発生因子には以下のようなものがあります。
- 尿路の形の異常(尿道狭窄)
- 尿路の感染症
- 水分不足や高カルシウム尿症などによるカルシウム濃度の高まり
- 「膀胱や尿道の病気」
前立腺肥大症による尿道の圧迫、膀胱炎、膀胱損傷、神経因性膀胱(排尿に関わる神経の障害により、排尿がうまく行われない病気)、膀胱憩室(膀胱の一部が膀胱外に飛び出たもの)など - 代謝の異常
- 副甲状腺機能亢進症やクッシング症候群などのホルモンの異常
- ステロイドなどの薬の服用
- 寝たきりなどで長期間横になる
- 手術などで膀胱に異物が入る(異物を核にして結石が発生することがある)
※以前はほうれん草などのシュウ酸の多い食物も結石の原因となると言われていましたが、現在では関連性はないとされています。
◆結石の巨大化
上記のような結石の発生因子は、結石が大きくなる原因にもなります。
結石はできた当初の小さい状態なら、尿路を傷つけたり詰まったりすることなく、そのまま尿と一緒に排出されます。しかし徐々に成長し大きくなっていくと、痛みや排尿障害などの症状を引き起こします。
結石が大きくなる主な原因は、「水分不足」と「尿の停滞」です。
体内の水分が不足すると、尿内のカルシウム濃度が高まり結石が大きくなります。特に、たくさん汗をかき尿量が少なくなる夏場に起こりやすくなります。
また、尿道狭窄や尿路の病気によって尿がうまく流れないと、尿が長く尿路にとどまり、その間にカルシウムが付着して石が大きくなります。また、細菌が繁殖しやすくなり尿路の感染症が起こります。
◆合併症について
尿管に結石が長期間とどまっていると、尿管や腎盂がはれて大きくなり、水腎症や水尿管症(尿管が普通よりも広がってしまうもの)を併発します。細菌感染が起こると急性腎盂腎炎も起こります。ほかにも膿腎症や膀胱炎が生じることもあります。
3.診断・治療・予防
◆診断
腹部の激痛や血尿といった特徴的な症状が見られれば尿路結石の疑いが高まるため、診断を確定するための検査を行います。
尿検査で血尿の有無を調るほか、X線撮影(レントゲン)、超音波検査、CTスキャンなどの画像検査で結石があるかどうかを確認します。
結石が小さく無症状なケースでは、健康診断で気づくことも多いようです。
【関連項目】
◆治療
結石が小さい場合は、水分を多量に飲んだり、尿管を広げる薬を飲んだり、適度な運動を行うなどして尿と一緒に排出させます。5mm以下の小さい結石ならほとんどは自然に排出させることができます。石が小さいと自覚症状がない場合も多いですが、激痛が見られるときは鎮痛剤も服用します。
結石が大きく、痛みや排尿傷害が起きている場合は、結石を摘出する手術を行ったり、自然排泄されるくらいまで小さく砕く治療法を採ります。
結石の摘出
結石が大きすぎず尿道の先端に近い位置にある場合、尿道口から鉗子を入れて結石をつまんで取り出します。結石が巨大だったり数が多い場合は、膀胱を開いて摘出する開腹手術を行います。
結石の破砕
尿道の奥に結石があるときは、膀胱まで押し戻してから結石を細かく砕き、自然排泄させる方法を行います。尿道から内視鏡を挿入して結石を砕く「経尿道的尿管砕石術」や、体外から衝撃波をあてて結石を砕く「体外衝撃波結石破砕術」があります。
◆予防
結石ができないようにするには、適度に運動する、バランスの良い食事をとる、水分を十分に摂取する(一日2~3Lが目安)など、排尿を促すための対策をとることが大切です。
こうした対策を行っていても、結石ができたり何度も再発を繰り返すようなら、病気や尿道狭窄などの尿の流れを妨げる要因を取り除く必要があります。
事前におなかの鈍痛や血尿・頻尿などの尿の異常が見られた場合は、腎臓に何らかの障害が起きているサインですので、早急に病院の泌尿器科を受診しましょう。
4.尿路結石データ
【受診科】
- 泌尿器科
【尿路結石の原因となる病気】
- 前立腺肥大症、神経因性膀胱、膀胱憩室、膀胱炎、高カルシウム尿症など
【尿路結石が原因で起こる病気(合併症)】
- 腎盂腎炎、水腎症、水尿管症、膿腎症、膀胱炎など