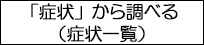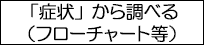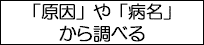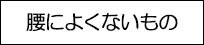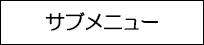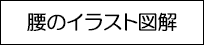腎静脈血栓症で腰が痛むケース
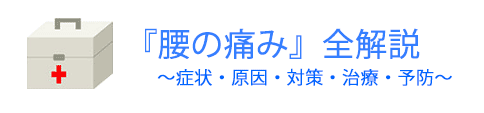
『腎静脈血栓症』の詳細 - 症状・原因・治療法
腰痛を引き起こす可能性のある病気や障害の一つに「腎静脈血栓症(じんじょうみゃくけっせんしょう)」があります。
ここでは、その特徴や腰痛との関連について解説します。
1.腎静脈血栓症が疑われる症状
腰の痛みのほかに、以下の様な症状・特徴が見られる場合、腎静脈血栓症が発症している可能性があります。
|
腎静脈血栓症は病気の進行が遅く、目立った症状がなかなか現れないことが多いです。
しかし、血の塊(血栓)の発生・増加が早い「急性」の場合は、腰痛や背中痛、発熱がみられるほか、上記のような排尿障害や尿の異常が現れます。
重症化すると、腎臓の機能が極端に低下した腎不全の状態になることがあります。
2.腎静脈血栓症とは? - 特徴や原因
左右2つの腎臓につながっている血管を「腎静脈」といいます。この腎静脈の片方、または両方に血の塊(血栓)ができて血液の流れが悪くなり、ひどい場合は血管が詰まってしまう病気が腎静脈血栓症です。
腎静脈の閉塞
◆血栓ができる原因
大人の場合は、血液の病気やネフローゼ症候群(※)が主です。
そのほか、病気の影響で血管が障害されたり、動脈硬化で血管が硬くなっている場合などに血栓ができやすくなります。また、免疫や遺伝子の異常によって血液が固まりやすい体質になることもあります。
大量のたんぱく尿が出て、血中のたんぱく質が減少するほか、血中コレステロールと中性脂肪値が増え、全身に強いむくみが起こったりします。また、血液が固まりやすい状況になるため血栓症の原因にもなります。
腎臓の病気によって腎機能が低下した場合や、腎臓以外の様々な病気に伴う症状の一つとして起こる場合があります。原因不明のケースも多いです。
腎静脈血栓症は子どもにも発症することがあります。多くは生まれつき血栓ができやすい要因をもっているためで、病気の進行も早い傾向があります。
3.診断・治療・予防
◆診断
尿検査における大量のたんぱく尿や、血液検査における低たんぱく血症、高コレステロール血症など、ネフローゼ症候群の特徴が見られた場合、腎静脈血栓症の発症が疑われます。
血栓ができているかどうかは、CTA検査やMRA検査などの画像診断によって確認します。超音波検査が行われることもあります。
CTA検査(3次元CT)
:あらゆる角度からX線(レントゲン)で撮影した画像をコンピュータで処理し、血管を立体構造として三次元に描き出す検査法。画像の陰影をはっきり映しだす造影剤を使うことで、血管を詳細に描き出すことができます。
MRA検査
:MRI検査と同じく磁気共鳴という原理を利用して、血管の様子を立体画像として映し出す検査です。
◆治療
おもに抗凝血薬を使って血栓を溶かす薬物療法を行います。治療後に再び血栓ができるのを予防する効果もあります。場合によっては腎静脈内の血栓を取り除く手術を行います。
滅多にありませんが、高齢者で高血圧症などの合併症がある場合は腎臓の摘出手術を行うこともあります。
治療によって血栓が解消されれば、この病気そのものが原因で死亡することはまれです。
死亡例として見られるのは、他の致死的な病気があったり、肺塞栓症などの合併症を起こしたケースです。
4.腎静脈血栓症データ
【受診科】
- 循環器内科、心臓血管外科
【腎静脈血栓症の原因となる病気】
- ネフローゼ症候群、動脈硬化、血管炎、糖尿病、腎臓がんなどの腎臓の病気、外傷遊走性血栓性静脈炎